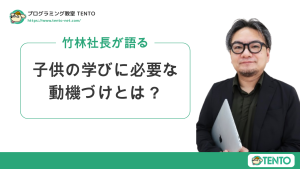子供の成長段階に合わせた「褒め方」の極意
皆さんこんにちは。今日は子育てにおいて非常に重要な「褒めること」について考えてみたいと思います。
子供をどう褒めるべきか、そもそも褒める必要があるのか、そして成長段階によってどう褒め方を変えていくべきかについてお話しします。
子供を褒める必要性
まず、子供とはどういう存在なのでしょうか。子供は基本的に「まだ物事ができない人」です。社会に対して何もできず、最初は何でも下手くそで、権利や権力も持っていません。
この「できない」状態から「できる」ようになっていくのが、大人になる過程です。
この成長を促すためには、「できるようになる」ことに対してポジティブなイメージを子供自身に持たせる必要があります。だからこそ、褒めることは非常に大切なのです。これが基本的なベースラインです。
成長段階による褒め方の変化
ただし、褒め方は子供の成長段階によって変えていく必要があります。
- 小さな子供(小学校低学年まで)
小学校3年生くらいまでの子供については、基本的にシンプルに褒めればいいのです。「よくできたね」「やったね」といった素直な言葉で十分です。これによって子供は「自分はうまくいっている」という感覚を持ち、学習に対して前向きになります。 - お世辞を見抜く段階
難しくなるのはそこからです。子供は成長するにつれて「この人は本当に私のことを見ているのか」「お世辞を言っているだけではないか」と考え始めます。この段階では、単純な褒め言葉だけでは効果が薄れてきます。
ただし、褒めることをやめるべきではありません。この段階の子供でも、自分のことを気にかけてもらっているという感覚を持つことは非常に重要です。問題は、言葉の文字通りの意味の裏にあるものを過剰に意識するようになることです。
効果的な褒め方のコツ
- 「ハッとさせる」褒め方
最も効果的なのは、子供を「ハッとさせる」褒め方です。「え?そんなところまで見ていたの?」と思わせるような、ありきたりではない褒め方をすることで、「本当に自分のことを見てくれている」と感じさせることができます。
例えば、子供がスクラッチでサイコロのプログラムを作ったとき、「サイコロの目が本物と同じように6の裏が1になっているのがすごいね」と、細部に気づいて褒めると、子供は自分の作品をしっかり見てもらえていると感じるでしょう。 - 自分の感情を素直に伝える
しかし、子供の活動をそこまで詳しく見ることは難しい場合もあります。そんなときは、「自分の目線」で褒めるという方法があります。
子供の作品や活動の中に、自分の好きなものや趣味に関連することを見つけたら、それについて言及するのです。例えば「あのマーク、私の好きなバンドのロゴに似ているね」といった具合です。子供がそれを知らなくても構いません。
重要なのは、あなたの感情が素直に表現されていることです。自分のパーソナルな趣味や好みに引っかかったことについて表現すれば、そこには嘘くさくない素直な感情が乗ります。これは敏感な子供ほど伝わるものです。
まとめ
子供の成長段階によって褒め方は変えるべきです:
- シンプルな段階:小さな子供には「すごいね」「頑張ったね」といった素直な褒め言葉で十分です。
- 複雑な段階:お世辞を見抜くようになった子供には、より具体的で、本当に見ていることが伝わる褒め方が必要です。
- どの段階でも:自分の感情に素直に、子供のことを本当に気にかけていることが伝わる褒め方をしましょう。
結果を褒めるか努力を褒めるかという議論もありますが、まずは子供がポジティブな気持ちになることが大切です。そして何より、子供を操作しようとするのではなく、自分の感情に向き合い、そこから生まれた言葉を素直に伝えることが最も重要なのではないでしょうか。
この考え方は、後でお話しする「叱ること」にも通じるものがあります。基本的に自分の感情に向き合い、そこから出てきたことを素直に子供に伝える—これが子育ての要なのかもしれません。
Q & A まとめ!
Q1. 子供を褒める必要は本当にあるの?
A. はい、あります。子供は最初は何もできない存在ですが、「できるようになる」ことにポジティブなイメージを持つことで成長が促されます。そのため、褒めることはとても大切です。
Q2. 褒め方は子供の年齢や成長段階で変えるべき?
A. 変えるべきです。小さな子供にはシンプルな褒め言葉が効果的ですが、成長するにつれて「本当に見てくれている」と伝わる具体的な褒め方が必要になります。
Q3. お世辞っぽくならない褒め方のコツは?
A. 子供の努力や工夫した細かな点を見つけて褒めたり、自分の感情や経験に素直に反応して伝えることが大切です。これにより、嘘っぽさがなくなり、本当に見てくれていると感じてもらえます。
Q4. 子供が敏感でお世辞を見抜いてしまう場合はどうすればいい?
A. 具体的な観察や、自分の好きなもの・趣味に引っかかった部分を素直に伝えることで、「本当に気にかけている」という気持ちが伝わりやすくなります
TENTOのおすすめポイント
- 日本初のプログラミング教室として2011年から14年の歴史を持つTENTOは、豊富な経験とノウハウで生徒一人ひとりに寄り添った指導を行っています。正解のコードを示すだけでなくこの記事のような解説ができるので意味の理解を助けます。
- 独自のオンライン授業システム「noiz」により、生徒と講師、さらに生徒同士のコミュニケーションをスムーズにし、学習環境をさらに向上させています。最初は一緒にコードを書いていてもすぐに自分の考えを反映しながらコードを作りはじめます。
- 体験授業の充実。まずは無料体験講座で教室の雰囲気を体験でき、リラックスして始められます。
- 機材サポート。PCの貸出やオンラインワークショップの開催など、学びやすい環境が整っています。
体験授業ご希望の方はお気軽にお申し込みください。
友達募集中・LINE公式アカウントはじめました!